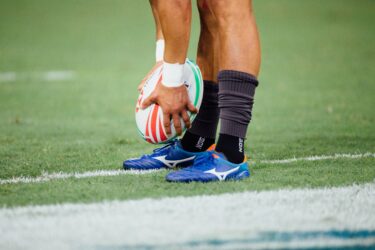①餃子耳とは?ラグビーの選手の耳が特徴的なのはなぜ?
餃子耳とは、ラグビーや格闘技などのスポーツで頻繁に見られる特徴的な症状です。
この状態は、耳の軟骨と皮膚の間に血液がたまり、腫れ上がった耳の形状が生じます。この血液による腫れを放置すると、軟骨にダメージが生じ、耳の形が変形したまま固定される可能性があります。
餃子耳になってしまう原因
ラグビーは、フィジカルな競技であり、大怪我を負う可能性があります。しばしば、選手たちは「餃子耳(ダンピングイヤー)」と呼ばれる耳の損傷を経験します。この現象は、ラグビー選手や格闘家など、耳に強い衝撃や物理的圧力が加わる競技をする人々にとても一般的なことです。
餃子耳は、細胞や血管を含む耳介部分の、硬い軟骨が損傷を受け、その形状が変わることによって発生します。
餃子耳は、痛みや腫れ、膿を引き起こし、臭いも強くなる場合があります。しかし、専門家の診断と適切な治療を受ければ、餃子耳の被害を最小限に抑えられます。
選手たちが餃子耳を防ぐためには、まず、ヘッドギアを装着することが必要です。
ヘッドギアを着用することで、衝撃を吸収し、耳を守るのに役立ちます。
②餃子耳を防ぐためには?

餃子耳を防ぐためには、耳をガードする方法以外にありません。
前述したとおり、餃子耳を防ぐにはへっとギアの着用をお勧めいたします。
内出血した血を抜いても、血が固まっていく現象はプレイをしている限り止められません。
耳の変形を防ぐためにどんな方法があるのか見ていきましょう。
₋1テーピング
耳を防御するために、テーピングで耳を守っている選手がいます。耳がこれ以上変形しないように、テーピングを巻いて耳をガードしていく方法をプロ選手たちは取り入れてる人が多いです。
ポジションによってテーピングをしている選手とそうではない選手がいます。
2ヘットギア
耳を守るもう一つの方法は、ヘッドギアです。ヘッドキャップという言い方をする人もいるでしょう。
頭をすっぽりと覆っているので頭部を衝撃から守ることもでき、耳も衝撃から守ることができます。
ちなみに、ヘッドギアは、高校生以下には着けることが義務化されているのです。
③ヘッドギアを使用しない理由
ヘッドギアの役割は、頭部への衝撃を緩和することや頭部の衝撃を予防するためと、耳の保護が主な役割になってきます。
ヘッドギアは、衝撃をくいとめるためにある程度の役割はあるものの、音が聞きとりにくいという弱点があることから、音が聞こえにくいと瞬時に判断して次のプレイに移行するときにズレが生じてしまうため、装着せずテーピングでガードする選手が多いようです。
選手にとって音が聞きとりにくいと勝敗を左右することも起こる可能性をひめているので、選手は多くのことを考え自分自身のプレイを活かすことができる方法を選んでいるといえるでしょう。
④餃子耳のラグビー選手は?
餃子耳になる選手はフォワードのポジションの選手です。その中でも2019年のワールドカップで大活躍し日本に勝利を導いた餃子耳の選手を紹介します。
1稲垣啓太選手:ポジション:プロップ

稲垣選手は、相手の一番前の選手と頭を交互に組み合わせ、パワーで相手陣まで押し込んでいく役割があります。
プロップはパワーが必要なポジションです。
スクラムで押し、モールで耐えるというパワーと忍耐力を持ち合わせているのです。そのパワーは太ももにも表れています。
『笑わない』選手として、知っている人もいるでしょう。
稲垣啓太選手は、ラグビーを愛する素晴らしい選手の1人です。
₋2姫野和樹選手:ポジション:ナンバーエイト

姫野の選手は、フォワードのリーダーの役割をしています。
スクラムを組んでいる最後に参加し体で相手を押し崩す役回りです。
ある時には、モールで起点になることも求められたり、総合的なゲーム展開能力が光っている選手です。
いつもにこやかな雰囲気がありますが、試合を展開させていくリーダーの役割をしているので勇ましさと頭の回転の早さのある素晴らしい選手です。
餃子耳の治し方
餃子耳の治し方については、早期の対策が重要です。まず、血液がたまった腫れた部分には冷却パックやアイシングを行うことで、腫れを抑えることができます。
冷却により、血管が収縮し、出血や浮腫みを抑制します。ただし、アイシングを行う際には、直接冷たいものを当てるのではなく、氷や冷却パックをタオルなどで包んで使用することが大切です。
その他にも、耳に衝撃を受けた場合にはすぐに専門医に診てもらうことも大切です。専門医の指導のもと、必要であれば耳の穿刺やドレナージなどの治療を受けることができます。早期の治療により餃子耳の進行を抑えて適切な形状に戻すことができます。
下記の動画も参考にしてみてください。
![]()
まとめ
ラクビー選手で餃子耳になっている選手は、ポジションによるものです。
隣の選手と耳を重ねるほど密着しなければモールは組めないので、耳がすれて血がたまったり、つぶれたりしていく餃子耳になる選手が多いです。
耳を守るには、テーピングとヘッドギアを装着するという方法があります。
しかし、ヘッドギアは耳を防御するには最適ですが、音が聞きにくいという弱点があります。
テーピングは、ケガのリスクの可能性は高まりますが、まわりの選手の声やレフリーが吹く笛の音が、聞こえにくいということはありません。
音が聞こえにくいということがないので、プレイに集中しつつ瞬時に対応ができる利点があるのです。
ラグビーは、ハードなスポーツです。
ラグビー選手は、ひとりはみんなのために、みんなはひとりのためにという精神で試合に挑んでいるからこそ、多くの人を魅了するスポーツに変化としてきたといえるでしょう。