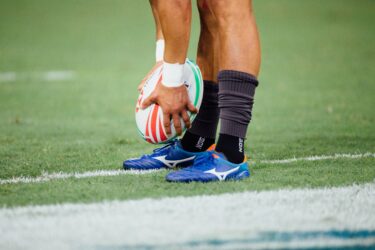ラグビーワールドカップの活躍で「ラグビーって何か面白そう!」という人が増えました。
そんなファン歴が短い人は、いわゆる「にわかファン」と呼ばれがちですが、ラグビー界としては、にわかファンでも大歓迎です!
ですが、にわかファンと言われたら良い気がしませんよね。
そこで今回は、ラグビーにわかファンと呼ばれないために、ちょっと難しいラグビーのルールを理解するために、ラグビーのルールを初心者でも分かりやすく解説します。
にわかファンを卒業するための基礎知識「ラグビーの原則」

この記事ではラグビーのルールでも、主な反則を分かりやすく解説します。
ですが、その前にラグビーの原則を知ることで「なぜこんなルールがあるのか」がより理解できるので、まずはラグビーの4つの原則を知りましょう。
4つの原則は
- 危険なプレーをしないこと
- 常に立った状態でプレーをすること
- 常にボールを奪いあえる状態であること
- 常にボール(ボール所持者)が先頭であること
これにはラグビー特有の理由があります。
ラグビーの原則1「危険なプレー禁止」
ラグビーは接触するプレーがとても多いです。
しかも、ラグビー選手はガタイが良く、体重がかなり重いので、普通の人同士がぶつかるのとは衝撃時のエネルギーが格段に違います。
走っていることもあるので、その威力は生身で小型バイクとぶつかるようなものです。
関連記事:筋肉フェチ必見!!筋肉むきむきなラグビー選手15名のプロフィール紹介
ですので、最悪の場合は脳に大きなダメージが加わり、命が絶たれることもあるのです。
だから危険なプレーは禁止となっています。
ラグビーの原則2「立ってプレー」
さきほど言いましたように、ラグビーは接触プレーが多くて非常に危険です。
そんなスポーツで、立ってプレーしている人と寝てプレーしている人が居たら、寝てプレーしている人がとても危険ですね。
しかもボールを奪いあうスポーツなので、もみくちゃになります。
だから立ってプレーすることがラグビーの原則1つなのです。
ラグビーの原則3「ボールは奪いあえる状態に」
ラグビーはとてもフェアプレイを重んじるスポーツです。
どのスポーツでも公平性は当たり前ですが、特にラグビーは危険ゆえ「ノーサイドの精神」が重要視されてます。
関連記事:ラグビー用語『ノーサイド』の意味や使い方を元ラグビー選手が解説!!!
ラグビーはボールを奪いあうスポーツ(正確には少し違う)ですので、ボールを常に奪いあえる状態にしないとダメ。という原則があるのです。
ラグビーの原則4「常にボールが先頭」
実はラグビーというスポーツはボールを奪いあってるように見えて、陣取り合戦なのです。
陣地の境界を示すための印がボールになっています。
ラグビーボールだけ前に投げて「そこまで俺たちの陣地な!」と言っても、それはフェアじゃありません。
仮にアリにしても、すぐボールを奪われて反撃されるだけですけど。(笑)
ですので、ラグビーボールは前に投げたり、前にパスする事は許されません。
主なラグビーの反則7選

さて、ここからは主なラグビーの反則を7つだけ解説します。
細かいルールはさて置いて、これから解説するルールを知っているだけでも「にわかファン」は卒業できます。
ラグビーのことをよく知っている人から一目置かれるでしょう。
ラグビーの主な反則1「ノックオン」
ノックオンは簡単で、ボールを前に落としてしまう反則です。
これはラグビーの陣取り合戦の原則上、フェアではないため反則を取られます。
同じような反則に『スローフォワード』があります。
スローフォワードは、ボールより前に居る人にパスすることです。
サッカーに当てはめるとオフサイドに似てますが、ラグビーのオフサイドは少し違います。あとで解説しますね。
ラグビーの主な反則2「ノットリリースザボール」
ノットリリースザボールは、名前の通りボールを離さないことによる反則です。
これもラグビーの原則から考えると、当然の反則
- ボールは常に奪いあえる状態にすること
- 常に立ってプレーすること
これらに違反します。
ボールを持っている選手がタックルされた時は、必ずボールをすぐ離さないといけません。
ボールを離させないために、邪魔をすることもあります。これはセーフ。
ボールを奪うこともOKです。ボールを奪ったらジャッカル成功と言います。
ラグビーの戦略上、わざと反則を受けるために離さないことも。
奪う側も、反則させたりボールを奪ったり、状況によって選びます。
ラグビーの主な反則3「オフザゲート」
オフザゲートは、ボールを奪いあう場面で横や斜めから取り合いに参加すると取られる反則です。
ボールを奪いあう時は、必ず自分たちが攻める方向に向かって真っすぐ突撃しないといけません。
これはラグビーの原則である、危険なプレーの禁止に沿ってますね。
四方八方から人が集まってきたら、とても危険です。
ですので、選手は必ず仲間の後ろから参加します。
ラグビーの主な反則4「オブストラクション」
この反則は、ボールを持っている人以外の邪魔をした時に取られる反則です。
味方のためにと思って、タックルしてきそうな相手選手の妨害をするのは禁止。
ラグビーはボール(陣地)を奪いあうスポーツですので、そもそものラグビーの原則から外れてしまいます。
もう1つ言えば『ボールに触れてない人はタックルなどされない』という前提で動いているので、そんな状態でいきなりタックルされたら受け身が取れないこともあって危険です。
ラグビーの主な反則5「オーバーザトップ」
オーバーザトップはラグビーでよく起こる反則の1つです。
動画で見てもらうと、分かりやすいかと思います。
ボールを奪うという行為はプレーの1つですので、必ず立った状態でしないといけません。
攻撃を続けさせないために、ついボールに覆いかぶさるよう防御してしまったら
ラグビーの原則「常にボールを奪いあえる状態」に反します。
ですので、このようなプレーは反則。危険なプレーにもなりかねないので、よくありませんね。
- タックルで倒された後の状況(ラックと言う)
- トライラインの手前
- 試合の終盤
このような人が密集する状況や、スタミナ切れの状態で起こりやすいです。
ラグビーの主な反則6「オフサイド」
プレーしてはいけない場所に居る人は、プレーの参加が禁止です。
参加してしまったらオフサイドの反則が取られます。
このオフサイドは、スクラムを組んでる時や、ラインアウト、ラックなど(ボールを奪いあってる時)それぞれでオフサイドラインが違います。
通常プレー時もオフサイドラインがあり、それは攻撃側だけ。ボールが基準です。
ただし、ボールを前に蹴った時は蹴った人がオフサイドラインとなります・・・ややこしいですよね。
ラグビーの主な反則7「ハイタックル」
ハイタックルは、首よりも上にタックルを入れる非常に危険な行為です。
ほぼ確実にイエローカードで、10分間の退場を受けます。
より悪質だと判断された場合は1発レッドで退場です。
ラグビーの原則、危険なプレーをしないことに違反してますね。
にわかファン困惑。反則があってもプレー続行する「アドバンテージ」

さて、主な反則については分かったかと思います。
ですがラグビーの試合を見ていて「反則があったのにプレー続行してるじゃないか!」なんて事があります。
どういう事?と思うでしょう。最後に、その疑問を解消します。
ラグビーのアドバンテージ
ラグビーには反則があっても状況によっては、すぐ審判が止めないこともあります。
これは反則があった直後、反撃が行われた時に発動するルールで、とりあえずその時の反則は保留にされます。
反撃中にミスがあったら、反則があった所まで巻き戻しに。
ただし、巻き戻しの有効期間は審判の判断で決まります。
これだけだと訳分からないと思うので、反則があった時の普通の対応方法からアドバンテージがある理由を解説します。
反則があった時は
- 反則があったらプレー中断
- 反則した相手チームにボールが渡る
- 試合が再開される
この手順で試合が再開します。
ですが、この手順だと反則したチームのディフェンスが整っています。
ラグビーはとても展開が速いスポーツですし、陣地(ボール)の奪いあいをするスポーツです。
ですので、ディフェンスが崩れていることも陣地を奪うためには有利な状況。
なのに審判がわざわざプレーを止めて、やり直すのは野暮というもの。
ということで、ラグビーは即反撃が行われた時はいちいち止めない事にしているのです。
アドバンテージの期限
反則後の反撃中、反則については一旦保留されているだけです。
攻撃側に回ったチームが反撃中にミスをしたら、反則があった時に戻ってプレイを再開します。
ですので、戦略的にアドバンテージとなったらリスクのある攻撃を選ぶことが多いです。
例えば、そのままボールを蹴ってゴールポストの間を狙うなんて大胆なことも。
入れば3点。外しても反則があった所からマイボールで再開できます。
もちろんボールを持って前に走ることもあります。
その時は、審判が「ここまで前に出たら反則時の利益を取った」と判断した瞬間、保留のままの反則とチャラにされて巻き戻しが行われません。
この瞬間をアドバンテージオーバーと言います。
オーバー後に反則すると、ボールは相手チームに渡ります。
このアドバンテージオーバーの判断は、審判それぞれの判断ですので明確に決まってません。時間が短いこともあれば、長いこともあります。
ある程度の基準として
- 反則された側が、仮にプレーを再開した時
- 陣地を前に広げられたであろう所まで
- ボール運びが進んだら
この3つの条件が重なった時、アドバンテージは解除されます。
まとめ ラグビーにわかファン、これで卒業

今回は7つほど反則を紹介しましたが、他にもまだ覚えきれないほど反則があります。
そしてラグビーの反則には審判のさじ加減で若干基準が変わるものもあります。
そのため、やはり全部のルールを覚えるということは困難を極めますが、今回紹介した7つの反則を覚えておけばコアなラグビーファンから「ラグビー知ってるな」と思われること間違いありません。
今回紹介した反則を覚えて、にわかファンを卒業しちゃいましょう!