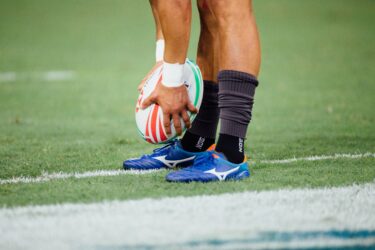2022年から開幕したラグビーの新リーグ「リーグワン」。
以前の「トップリーグ」と何が違うのか気になる人も多いのではないでしょうか。
この記事では「リーグワン」設立の目的から今後の課題まで詳しく解説していきます!
リーグワン設立の目的
ラグビー日本代表が、ワールドカップ2015年大会で南アフリカを撃破、さらには2019年大会では初のベスト8進出を果たしたことはまだ記憶に新しいでしょう。
日本全体が熱狂の渦に包まれたと言っても過言ではありません。
ところが野球やサッカーと違い、ラグビーの盛り上がりはなかなか定着しないのが現状です。
「リーグワン」は日本におけるラグビーの普及と強化を目的に、新たに設立されました。
リーグワン設立の目的を知るうえでポイントになるのが次の二つです。
1、地域密着によるファン拡大
トップリーグでは、企業名がチーム名の愛称となっていましたが、リーグワンではチーム名に必ず地域名が入ります(企業名を入れるのは任意となっています)。
たとえば「パナソニック ワイルドナイツ」は「埼玉パナソニック ワイルドナイツ」に変わりました。
本拠地をトップリーグ時代の群馬県太田市から埼玉県熊谷市に移し、熊谷ラグビー場を改修してホームスタジアムとしています。
また、リーグワンでは「ホスト&ビジター制」(ホーム&アウェイと同義)で試合が行われます。
野球やサッカーと同じように地域密着を図り、最近では地域清掃やラグビー教室など、ファンとの交流を深めるチームが増えてきています。
あこがれの選手と触れ合う機会が増えるとともに、ファンの拡大を目指したリーグと言えるでしょう。
2、世界レベルへの飛躍
東京サントリーサンゴリアスに加入した元オールブラックスの「ダミアン・マッケンジー」のように、リーグワンには、世界のスター選手が次々と参戦しています。
世界最高峰のプレーが日本のスタジアムで観られるのは、ラグビーファンにとってはたまらないものです。
日本人選手と世界のスター選手が競い合うことで、選手はもちろんチーム全体のレベルが上がっていくのは間違いありません。
世界レベルのスキルとコンタクトレベルを肌で体感することで日本のラグビーレベルの向上図れます。
また、リーグワン全体のレベルが上がれば、当然日本代表の強化にもつながっていくでしょう。
逆に、リーグワンから世界のリーグへ参戦していく選手も増えていくのではないでしょうか。
リーグワンの今後の課題
ここまではリーグワン設立の目的についてお伝えしてきましたが、今後の課題として考えられるのが「地理的な偏り」です。
DIVISION1(1部リーグ)には、12チームのなかに「東京」と名のつくのが4チームあります。
さらに「東葛」「浦安」「埼玉」「横浜」を含めると、首都圏だけで8チームです。
DIVISION2やDIVISION3を加えれば「岩手」「広島」「福岡」などが入ってきますが、それでも北海道や四国にはチームが存在しません。
たとえばワールドカップなら「国」対「国」の対立関係が生まれることで応援に熱が入ります。大学選手権なら「早稲田」対「明治」のように。
リーグワンは、企業名ではなく地域名を略称にしているため、どうしても「東京」対「東京」のように対立関係が不明瞭になってしまうのではないでしょうか。
また、「チーム名が長すぎる」、「区別がつきづらい」など現状ではあまり良い評価といえないのが現状。
しかし、そのような評判の中でも真摯に地域性や社会性に向き合い各自治体と協力を模索する努力も垣間見える。
少なくとも最も観客人数が期待されるDIVISION1では、チームの地理的な偏りやチーム名の改善などの課題が残る。
リーグワン まとめ
ラグビーの「ノーサイド」とは、試合が終われば敵も味方もなく、お互いの健闘を称え合うこと。
また「One for all All for one」とは、一人はみんなのために、みんなで一つ(勝利)のためにという意味のことです。
この二つの精神は、日本人の文化にとてもマッチしているといえるでしょう。
だからこそ日本代表の活躍は、国民全体にあれだけの共感を得ることができたのではないでしょうか。
リーグワンがますます発展し、選手とフォンたちが一体となった日本のラグビーが2023年ワールドカップフランス大会で熱い戦いをすることに期待したいですね!